これから「社会福祉士」を取得しようと思っている方。具体的にどのようなことを学ぶのか、知っていますか?
私は、福祉とは離れた業界で仕事をしていましたが、あるきっかけで専門学校に行き「社会福祉士」を取得しました。
入学前は、ネットや本でざっくりと調べ、「困った人に対して、話を聞いて、一緒に解決していく相談員?」「社会保障の制度や医療・心理学も学ぶ?」など、何となくのイメージをもっていました。
しかし、専門学校に入学して実際に勉強をしてみると、「こんなことも勉強するんだ…」と思うことが多くありました。(そもそも私の下調べが悪いのですが)
そこで、これから「社会福祉士」の取得を考えられている人に向けて、「こんなはずではなかった😫」とビックリ・後悔しないように、学習内容をご紹介していきたいと思います。
今回は、社会福祉士の専門科目について記載します。(今は新カリキュラムに移行途中なので、これから大学に行かれる方、編入される方は少し変わっているかもしれません)
- 社会福祉士の取得を考えている
- 福祉に関する仕事をしたことがない
- 具体的にどのようなことを学ぶのか知りたい
共通科目についてはこちら↓↓↓
各専門科目ごとの学習内容
社会調査の基礎
- 統計法、調査における倫理や個人情報保護
- 調査の種類と特徴(個人・集団インタビュー、アンケート、観察など)
- 調査票の作成・配布・回収・データ解析と留意点
ネットや用紙・対話など、さまざまな調査方法におけるメリット・デメリットや、質問が誘導的にならないようにする注意点、アンケート結果の分析・その信頼性などについて学びます。
平均値と中央値の違い、相対度数や偏差など、数学的な部分があるので、馴染みのない人は理解するのに時間がかかります。国家試験では、おおよその特徴が理解できていれば大丈夫です。
相談援助の基盤と専門職
- 国家資格としての社会福祉士の位置づけ
- ソーシャルワークの基本概念・機能、これまでの歴史・成り立ち
- 人権尊重、社会正義、権利擁護、自己決定などの理念
- 倫理綱領・行動規範と倫理的ジレンマについて
法律による社会福祉士の定義や罰則規定、国際的なソーシャルワークの定義について、また日本や海外のソーシャルワークに関する歴史を学びます。 様々な人や業績・団体について覚えるのが大変でした。
社会福祉士としての倫理や行動規範が明文化されているので、今後働くうえでの指針として、また自己の振り返りとしても役立ちます。
これから資格取得を目指す人は、「日本社会福祉士会が提示している倫理綱領」をご覧になって下さい。どんな資格なのか少しイメージが湧くと思います。↓↓↓
相談援助の理論と方法
- 人や環境、社会資源などについての見方・関係性
- 相談援助に関する技法、援助プロセス、記録や効果測定
- 援助者側の自己の捉え方、援助関係について
- 相談援助のための面接技術、集団の活用
- ネットワーク形成、社会資源の活用や開発
- 各実践モデルの起源・理論・対象や支援の展開
- 事例研究・分析
ものごとを捉えるとき、どうしても個人的な生育環境で培われた見方・感情になってしまいます。しかし、ソーシャルワーカーは相手の立場に立った多面的な捉え方が必要です。人は社会と密接に関わっており、個人を取り巻く人や環境に対し、お互いに大きな影響を及ぼしあっていることを学び、広い視点でものごとを捉える考え方を学習します。
面接技術は、面接する環境、質問の仕方、表現、言葉以外のコミュニケーションなどについて学びます。また、実践モデルやアプローチはそれぞれの提唱者や特徴について学習します。長所に焦点をあてるストレングスモデル、本人の持っている力を引き出すエンパワメントアプローチなどがあります。
福祉サービスの組織と経営
- 一般企業と福祉サービス企業の違い
- 福祉に関わる法人とそれぞれの特徴
- 人・サービス・財務のマネジメント、質の評価や苦情対応
- 情報管理、公表制度について
各法人の概要、設立基準や役員などの条件、税制優遇措置、補助金など学びます。また、組織や経営理論について、学者が提唱したものを広く薄く学びます。財務諸表にも触れますが、代表的な用語の意味程度です。労働基準法などについても、簡単に触れています。
高齢者に対する支援と介護保険制度
- 高齢者に対する理解(身体・精神)、相談支援について
- 高齢者福祉に関する歴史、法律、組織や役割など
- 介護保険法と各種サービスについて
- 介護の概念や基本的な知識・方法
- 認知症・終末期ケア、住環境などのあり方
平均寿命や高齢化率、介護サービスの利用状況などの統計、移動・食事・入浴などの介護の基本的事項について学びます。また、認知症の特徴や関わり方・支援制度、介護のための住環境の整備(段差、通路幅、色彩など)についても学習します。
そして一番のボリュームは介護保険制度です。仕組みや財源、費用負担、介護認定のプロセス、各種サービス内容、各介護施設、保険料・介護報酬と支払いの流れ、行政や関連団体・各専門職の役割などがあります。
その他、老人福祉法や高齢者虐待防止法、バリアフリー、高齢者住まい法について学びます。
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
- 日本と諸外国における家庭福祉の歴史
- 子育てや成長・発達・環境の現状
- 子どもの権利や保護について
- 子どもに関する法律と施設・組織の役割
- 相談援助の方法について
出生率や乳児・妊産婦死亡率、いじめの件数、児相への相談件数、DVなどの各種統計やこれまでの児童福祉に関する歴史について学びます。
また、児童の権利に関する条約とたくさんの法律〔児童福祉法、児童虐待防止法、DV防止法、母子父子寡婦福祉法、母子保健法、児童(扶養)手当法、特別児童扶養手当法、次世代育成支援対策推進法、少子化対策基本法、売春防止法〕や施設があり、とてもボリュームのある科目です。
その他、行政・児相・家庭裁判所・各施設や専門職の役割と連携について学習します。
就労支援サービス
- 雇用・就労に関する統計、法律
- 障害者・低所得者などの就労支援制度や組織について
- 各施策における機関、専門職と役割
労働力人口、完全失業率、有効求人倍率、非正規雇用、ニート・フリーター、共働き世帯、障害者雇用状況などの統計について学びます。また、就労訓練やお試し雇用などの制度や市町村・ハローワークなどの役割や連携、各専門職について学習します。
更生保護制度
- 更生保護法・医療観察法の目的、関係機関や専門職の役割
- 少年法について、児童福祉法との関わり
- 少年司法、刑事司法(成人)、医療観察法の手続きの流れ
- 犯罪予防活動、被害者に対する支援について
更生保護は刑務所・少年院などの施設ではなく、社会の中で処遇が行われ、自立や更生を助けるものになります。医療観察法は心神喪失で重大な犯罪をした人に対する処遇です。
刑法犯の認知・検挙件数、内容、年齢構成などの統計、罪を犯してしまった人に対する刑事司法などの流れ、警察・検察・児相・家庭裁判所・医療機関・民間の役割や専門職について学びます。
相談援助演習
- 他の科目で学んだことを演習によって総合的に理解する
- 具体的な課題について、事例検討などを通じて実践力を高める
- ソーシャルワークの価値に基づく支援・自己評価と改善に役立てる
社会福祉士として、課題や状況を多面的に理解し、説明する能力が必要になってきます。そこで、事例や映画などを通して、グループワークやロールプレイを行います。相談支援のプロセス、ソーシャルワークの倫理や原則にのっとっているか、根拠(理論・モデル)に基づいているか、自分や相手の立場となって考えることが出来ているか、演習を通じて体感的に学んでいきます。
意見が分かれることもありますが、自分では感じ取れなかった視点、先生の指導・介入による気づきはとても役に立ちますし、有意義な科目であると思います。
相談援助実習
- 実習先の事前情報整理(利用者・役割・地域の特徴・関係機関など)
- 実際の現場における支援、チームアプローチなどについて
- 事例研究を行う
自分の興味のある分野について、2か所で実習を行います。他の生徒もいるので、必ずしも希望通りとなるわけではありません。実習期間ですが、私の場合は1か所目が16日間、2か所目が8日間でした。
実習施設が決まったら、その施設に関する情報を事前に整理し、学びたいこと・体験したいことをレポートとしてまとめます。その後、実習先の指導者と打ち合わせをして、調整していきます。
実習中は指導者のもと、利用者と接したり、会議や関係機関への同行などを行います。日々指導者と振り返り・レポートを作成し、実習で得た具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化できるよう努めていきます。終盤では、特定の利用者について、どのような支援展開をしていくか事例研究を行っていきます。
終了後は総合的なレポートの作成や皆で発表会を行い、それぞれの実習について共有します。
終わりに
社会福祉士は多くの法律や社会情勢、調査の仕方や経営論など、幅広く学んでいくことが伝わったのではないでしょうか。これから取得を目指す人の参考に、少しでも役立てて頂けたら嬉しいです。
参考になる書籍の一部をご紹介↓↓↓
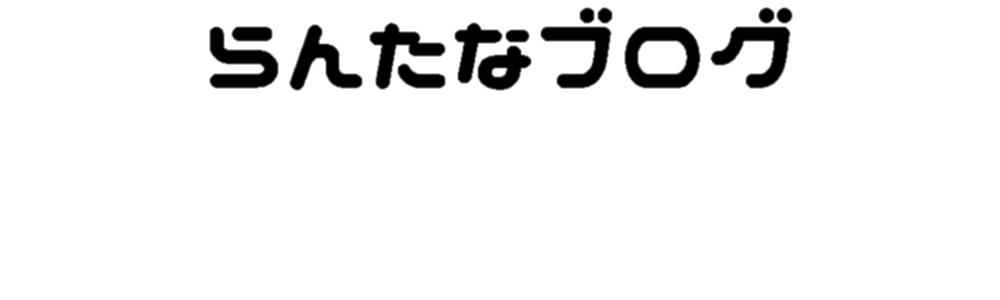
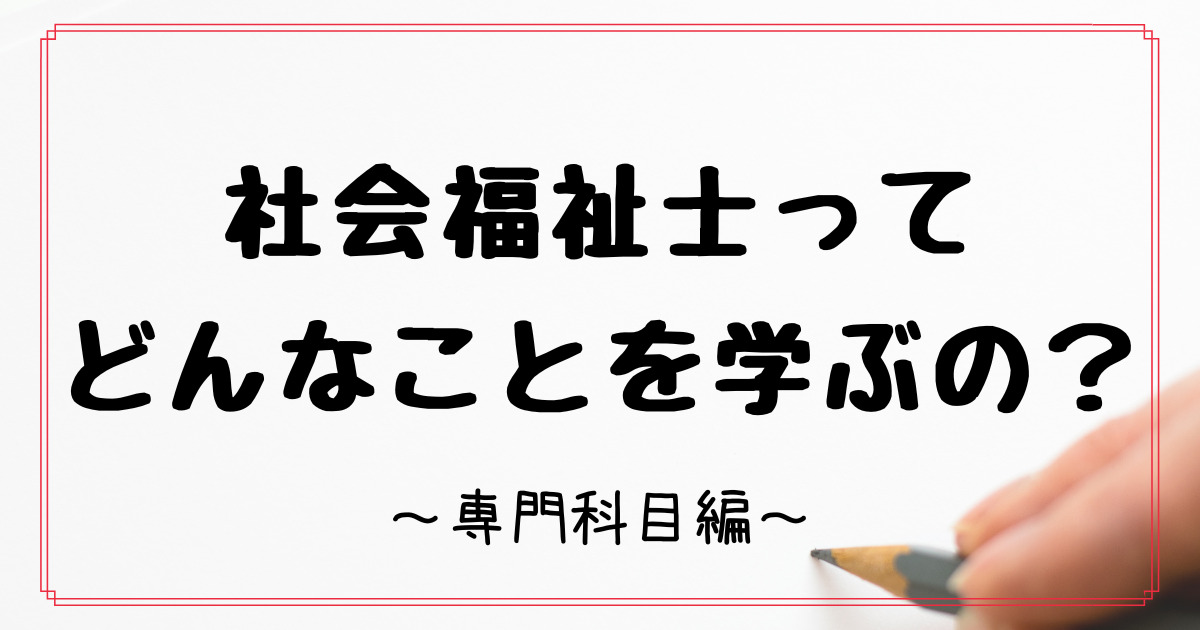
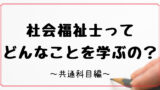

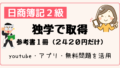

コメント